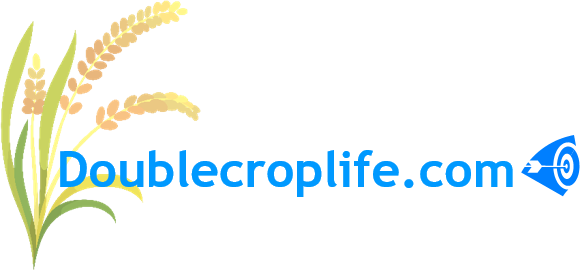生成AIネイティブの基礎学習能力
昨今話題の生成AI。私も試しに使ってみたのだが、かなりの優れモノだ。ちょっとした調べものにこれまではGoogle検索でキーワードを入力し、出てきた候補の中から自分がイメージしていた答えを順番に探していくのが普通だった。また、時折スポンサーのおすすめページにはまってしまったりしながらも、特に目的を定めずネットサーフィンをするならば、これはこれで大変便利なツールだ。
以前は、いくつかの候補から自分の答えを見つけるのもある程度容易だったが、ネット上に膨大な数の情報が飛び交う現在では、それさえもかなりの労力を要し、いつまでたっても必要な答えが見つけられないという経験は、皆さんも幾度となくしているであろう。
かく言う私もこのところそんな事が続いていたので、まずは試しに秋に計画している東北旅行の候補先を、大分昔に使ったChatGPTに改めて聞いてみることにした。相談ワードは「横浜から仙台、平泉への旅行プランを教えて」「往路は新幹線、復路は飛行機の予定」だけである。すると2泊3日の旅行プランがほんの数十秒で出てくるのである。そこには移動手段や観光スポット、所要時間に料金まで記載されている。
また、特に行きたい観光スポットや帰りたい時間、交通手段等の制約条件や希望を伝えれば、それに合わせて旅のプランをリコメンドしてくれるので、ガイドブックをじっくり読み込まなくても、かなりのレベルの旅行プランが出来上がってしまうのは、何とも驚きだ。
この様なアウトプットが出来たので、次はもう少しビジネス寄りの業務についてトライしてみることにした。次のテーマは新たに事業を始めるにあたり、財務諸表は読んだことがあるが、実際の入力作業は経験が無いという、ある意味素人が一から会計システムを使いこなせるのかという問題だ。今回は最初に生成AIへ、「私は個人事業を開業し、これから青色申告の帳簿付けを始めるので色々教えてほしい」という自分の状況を説明した。生成AIに対して私はこう言う人間であると宣言することにより、今後の質問は基本この件に関するものだと認知してもらうことで、より期待する答えが得られ易くなるのではと考えてのことだ。
そうすると、生成AIからは「青色申告スタート、おめでとうございます!」と言うコメントと共に、「青色申告とは」「メリット」「手続き」の説明、そして何から始めれば良いかなどの助言が返ってくる。また、事業内容や導入予定の会計ソフト等の質問が来て、それに答えるとソフトの特長や使い方、勘定科目の扱い方等も説明してくれるのだ。その後も個人口座の扱い、会議費の扱い等ちょっとした疑問を質問しても、これも丁寧に回答してくれる。勿論、会計ソフトにも使い方のQA等はあるが、やはり事例やサンプルを読んで、自分で自分が必要とする答えを探し出さないといけないのは、素人にはかなり難しい。生成AIの回答には、ある程度説明も付けられていることで、理解し易いと言う利点もあるように感じる。
そして、次は私の知人の例だが、こちらは生成AIに業務システムを開発させようという試みだ。彼は現場の営業マンだが、プログラミングの経験はゼロ。生成AIには興味があり、日常の色々な場面で流暢に活用している程度の経験者だ。ある業界における商談で大量の資料から提案要件を抽出し、自社の資産と比較して提案書のたたき台を作成するというシステムだ。従来は専門の要員が人手で過去の例等を参考にしながら実施していたものだ。システム化するにあたっては、仕様書の作成から始めて、設計書、プログラミング、テストと全ての工程を生成AIとの会話で行ったと言うものだ。開発は通常の営業業務と並行して行ったとのことで、その間に日程が空いたり、過去の記憶が曖昧になったりすることも当然起こるので、AIにはタイミングタイミングで業務内容の引継ぎを内部でさせたり、変更や追加は細かく記述させるなどの工夫もかなりしたとのことだ。その結果、構想から約2か月で開発が完了し、現在現場でPOCの実施中とのことだ。
この様に生成AIの利用事例を比較的簡単な日常使いから、かなり高度な業務レベルまで見てきたわけだが、ここで気付くのは、所謂プロの代わりを生成AIがこなしているという事実だ。一つ目は旅行プランナー、2つ目は税理士、三つめはプログラマーと専門職に近い職種だ。約10年前にオックスフォード大学のマイケル・オズボーン博士の「コンピュータ、AIの普及により将来なくなる可能性のある仕事」の予測では「税理士」「公認会計士」に近い仕事やプログラマー等も含まれていたので、まさにその現実が近づいてきた感がある。時代はまさにSF映画の世界へと足を踏み入れ、私たちの仕事やキャリア形成の在り方も大きく変わろうとしているのかも知れない。
ただ、ここで私たちが注意しなければいけないことは、勿論このAIをどう使いこなしていくかと言うことだ。
AIが人間を超えるという所謂「シンギュラリティ」だが、米国の近未来学者レイ・カーツワイルによれば2045年にも到来すると予測されており、また、他の有識者によれば2030年代という説や来ないという説など様々だ。しかしながら、この便利な知能を私たちは好むと好まざるとに関わらずこれから益々使っていくと言うのは、ほぼ疑問の余地を挟むところが無い意見だろう。そう言った世の中の流れにおいて、今回の事例を通じて感じたことは、私たちが如何に物事を「正確に理解」し、「正確に伝える」ことが出来るかと言う能力を有しているかが、非常に重要になるということだ。皆さんも感じていられる通り、生成AIとは会話相手であり、相談相手であり、先生であるということだ(最近のChatGPTは妙に馴れ馴れしすぎると言う意見もあるが)。従来のGoogle検索のように関連する単語を並べて調べるということではなく、生成AIにおいては、会話を通じて答えを導く、あるいは自身の満足感を得るというプロセスがとても重要になる。当然のことながら、単語を羅列しても会話は成立せず、会話を繰り返すことにより、最適な解をお互いに導いていくことができるのである。それ故に、自身の考えをきちんと整理して相手に伝え、相手の発言を正しく理解して次の会話につなげる能力が非常に重要になると思えるのである。また、この能力により、AIによる誤った情報の提供、所謂ハルシネーションを避けることも可能になっていくと考える。昨今、「生成AIに論文を書かせた学生が単位を落とした」「AIに宿題をやらせた」などと言う話題を良く耳にする。こういった事象から、子供たちが益々自分で考えることをしなくなり、学力の低下が進むのではないかと危惧する向きもあるかもしれない。しかしながら、逆に考えると、子供たちは「正しく考える」、「正しく伝える」と言う能力を磨いていかないと、AIを使いこなすこともできず、益々情報デバイドの世界に落ちていくとも言えるのではないだろうか。
そう考えると、学校教育においてもその重点は、これまでの「記憶する」と言う分野から、「考える、創造する」と言う分野に視点をシフトしていく必要が大いにあると感じている。近年の義務教育課程においても、「考える授業」の視点で「主体的・対話的で深い学び」を重視した、アクティブ・ラーニングの手法などが取り入れられているとのことなので、「生成AI」時代の新たな教育カリキュラムが生まれてくるのかもしれない。
近い将来、AIネイティブの大学生が選ぶ人気職業ランキングは「IT関連」、「コンサルタント」から「ジェネレイティブAIワーカー」とか「プロンプトエンジニア」とかになっているかもしれないと思うのは私だけだろうか。